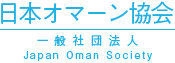不思議で魅力的な国オマーン
現在リニューアル作業中のため旧サイトをご覧ください。
不思議で魅力的な国 オマーン
不思議の国オマーン。私たち日本人の想像を超えた国土と歴史、そこに暮らし続けるアラビアの人々は、過酷な砂漠の地に井戸を掘ってわずかの農地を耕し、小さな舟を駆ってアラビア海からインド洋に交易ルートを開き、イスラム文化をアフリカ大陸から東南アジアの地へと広め、
一大海洋王国として華麗な花を咲かせた。
シンドバットたちがつくりあげた海洋王国オマーン
アラビア半島の東南端にある天然の良港マスカット。アラブ大帝国の都バクダットとインドやアフリカ東岸を結ぶ交易の拠点として栄え、この海廊を通って多くの商人や物資が東西南北へと行き交った。
世界文明の発祥の地のひとつであるメソポタミア平原はティグリス川とユーフラテス川のもたらす肥沃な土壌によって1万年もの昔から農耕が始まり、5000年前からさまざまな民族の王国が征服と滅亡を繰り広げてきた。古バビロニア王国、アッシリア帝国、ペルシャ帝国、そしてアレキサンダー大王による征服やローマ帝国の支配を経て、再びペルシャのササーン朝に征服された。その後アラビア半島に興ったイスラーム共同体の大征服活動によってアラブ軍に634年占領され、イスラームの支配下に入った。イスラム世界では661年にウマイヤ朝が成立したが、750年にはアッバース朝がこれにとって代わった。この新しい王国の2代目カリフとなったマンスールが新しい王都として762年から766年にかけて築いた一大計画都市がバクダッドである。
バクダットは唐の長安をも凌ぐ発展を続け、最盛期の9世紀から10世紀には100万~150万人の人口を擁するアラビアンナイトの物語るように世界で最も華麗で豊かな都であった。遠く中国やエジプト、イスタンブールとラクダを使って様々な交易が行われ、南方からは舟に乗って象牙、乳香、香辛料、白檀、真珠、宝石、金といった宝物がもたらされた。千一夜物語に出てくるシンドバッドの7回の冒険は、大海原を超えて交易の旅をしたアラブ商人の伝える土産話の中から生まれた。
アラビア半島と対岸のペルシャ(現イラン)との間にはホルムズ海峡がある。両民族はバクダッドの支配を巡り抗争を続けたが、この狭い水路の航行を巡っても、双方は常に緊張関係にあった。マスカット港は、アラブ人にとってはインド洋に出ていく拠点として、極めて重要な位置にあることが地図を見ればよく分かる。
この国には川がない
オマーンは砂漠の国で雨季は無く、ほとんど雨が降らない。
首都マスカットの南から西北に日本の南アルプスのような険しい山脈が300㌔も連なり、その東側に僅かに畑が続く。農地は国土の0.3%しかない。28万人の農民が井戸を掘って細々とナツメヤシや麦、ジャガイモ、野菜を収穫し、家畜として主にヤギを飼う。この広大な岩山にはV字状に直立した長い角を持つアラビアンオリックスが棲息していたが、不幸にも牛の仲間で肉が美味しかったために、今では野生は絶滅してしまった。隣国のアブダビで保護されて繁殖に成功し、日本のトキと同じように自然に戻す試みが続けられている。
マスカットから西の隣国イエメンまで続く1,200㌔の海岸線は、川の浸食がもたらす平地や砂浜が無く、砂漠がいきなり絶壁となって海に落ち込む。植物も動物もほとんど見られない。町も港も少なく、漁業も行われていない。農耕も牧畜も拒む広大な砂漠の覆われたオマーンは、海洋民族として活路を交易に求めざるを得なかった。
かつて地中海文明を支えたのは巨木レバノン杉であった。フェニキア人の交易船もエジプト遺跡の船もこのレバノン杉で造られた。アラブ人がバクダットから川を伝って海に出るのは木造舟ではなくナツメヤシの筏であったかもしれないが、海廊を伝ってアフリカやインドにまで交易に出掛けるには、帆を張った舟が必要である。シンドバッドは自分の舟ではなく、「乗り合いの交易舟」に荷物を積んで往来している。アラブの舟乗りたちが、アフリカやインドや東南アジアにまで出かけざるを得なかったのは、舟をつくる木材を求めるためであったのかもしれない。
マスカット港は2000年以上の歴史を持つ
岩山に囲まれた小さな入り江に、海廊を巡る交易商人たちの寄港地として紀元前200年ころに開かれた。王宮と砦を持つ港町は1㌔四方にも満たない。しかし今や国民の3分の1が暮らす人口100万近いオマーン唯一の大都市である。人々は交易がもたらす富によって、王宮から少し離れた山間や海岸沿いに新しい町を広げていった。
かつてインド洋を取り巻く各地に交易の拠点を構えたオマーンは、最盛期の1832年には、王宮をアフリカ東岸タンザニアのザンジバルに移した。それは東京からから香港に遷都したほど遥かに遠く、オマーンはそれほど広大な海域を支配する一大海洋王国であった。都をアフリカに移したのはマスカットが狭すぎて水や食料確保に制約を感じたからか、或いは盛んになる奴隷貿易に力を注ぐためであったのかもしれない。
しかし一時期そのオマーンはポルトガルの支配下に置かれ、インド洋の海洋交易権を奪われたことがあった。ヴァスゴ・ダ・ガマがポルトガル国王の命により1498年にインド到着できたのは、オマーンの交易舟の水先案内によってであった。ところがガマの帰国報告を受けて、香辛料貿易がいかに富をもたらすかを知ったポルトガルは、1509年にオマーンに攻め込んで来たのである。かつてスペインがインカ帝国を滅ぼして、神殿を壊して金をごっそり奪い去ったように、ポルトガルはマスカット港を奪い取り、要塞を築いて海上交易を150年にわたって支配した。アラビア人は1650年にマスカットを奪還し、ポルトガルの支配から国土を回復した。こうしてオマーンはヤールビ王朝が始まった。その後1749年サイード朝が成立し、イギリスが世界の覇権を握る19世紀末までインド洋全域を商圏とする 海洋王国として繁栄を続けた。
帆舟の時代は終わり、海廊交易は衰退していった
スペインのあるイベリア半島は、フェニキア人が紀元前500年ころ植民都市を築き始め、ついでギリシャ、カルタゴ、ローマに支配された。ローマが衰えると北ヨーロッパから西ゴート族が侵入して王国を築いた。そのゴート族の王国も711年に北アフリカから侵入したアラブ人に滅ぼされ、およそ8世紀にわたって、イスラムが支配した。長い再征服運動(レコンキスタ)の戦いを続けて、キリスト教徒たちは少しずつイスラム勢力から国土を回復し、ついに1492年アラブ人をイベリア半島から追い出し、スペインとポルトガルが成立した。その余勢をかって、スペインとポルトガルは海の外へと勢力範囲の拡張へと乗り出した。
大型の帆船により、アメリカ大陸を発見し、アフリカの南端を回ってインドへと進出し、スペインとポルトガルは世界の海を制覇した。その後、次第に力をつけたオランダがそれにとって代わった。さらに帆船に代わって蒸気船が活躍する時代に入ると、世界の7つの海の覇権はイギリスへと移っていった。
オマーンは1856年にアフリカに遷都したサイード国王が死去すると、ザンジバルとマスカットが対立、広大な商圏を支配した海洋王国は分裂してしまい、急速に衰退していった。そして1891年には海廊交易はイギリスに奪われ、その保護国にされてしまった。20世紀に入っても、内戦や地方の反乱が起きるなど、オマーンは苦難の時代が続いた。
宮廷革命で新しい国造りが始まる
1968年にイギリスは「スエズ以東撤退宣言」を発表した。アラビア半島にあるイギリスの保護領も一斉に独立に向けて動き出し、オマーンは1970年、宮廷革命によりカブース皇太子が30歳でサイード朝の第8代目の国王に就任した。新国王は父親の鎖国政策を転換して、新しい国造りに乗り出し、翌71年にはイギリスから独立し、国際連合にも加盟した。内陸の砂漠で1967年に石油生産が開始され、その後2000年には可採量が140年とみられる大規模な天然ガスの生産と輸出も始まり、その外貨収入で経済建設を推し進めることが可能になった。
国王は絶対君主制を敷き、兄弟がいないために自ら首相、蔵相、外相、国防相を兼ね、地方巡業に毎年出掛けて、国内融和に腐心し、国民からは厚い信頼を得ている。国王は従妹と一度結婚したが、離婚後は独身を貫き、子供もいない。オマーンの国政は王族・英国人などの顧問や官僚組織に支えられて、国王の親政を続けてきたが、1981年には諮問委員会を設立し、91年には諮問評議会に改組するとともに、95年には女性議員を任命して女性の地位向上にも努めている。1996年には成文憲法である国家基本法を公布した。さらに2011年3月にカブース国王は議会に立法権を付与する勅令を出した。兵役はないが、国王親衛隊と 陸・海・空軍を合わせて約46,000人の兵力を持っている。
若者の教育に将来を託す
石油と並んでこの国の財政を支えるのが天然ガスの輸出である。その一番の輸入国が日本である。その石油は後10年、天然ガスもいずれは無くなってしまう。新たな油田やガス田が発見されること、全く手つかずの経済水域で地下資源の開発を進めることの可能性はある。しかし、石油や天然ガスの輸出で潤っている間に、将来に備えてどのような国造り進めるかは極めて大切である。
オマーンは日本の国土の4分の3の広さがあるが、人口は300万人にも満たない。そのうち90万人が外国人である。イスラム教徒の国であり、およそ4分の3がイバード派、4分の1がスンナ派に属している。
マスカットを中心に、道路網や港湾、街づくりといったインフラ整備は精力的に進められているが、生活用水は海水の淡水化によって賄われ、電力はすべて火力発電である。経済規模が小さいために、新しい産業を興すには様々な制約を伴う。
とても親日的で、西洋だけを向くのではなく、日本に学ぶことに意欲的である。近年は日本に若者を留学させる試みも始まった。石油や天然ガスといった地下資源の輸出だけではなく、水資源の確保、新しい輸出農産物や広い経済水域を生かした漁業資源の開発といったことも、日本として取り組める援助かもしれない。
これからのオマーンと日本の国造りのために、経済交流だけではなく、教育・文化・スポーツ・科学技術など様々な面で若者同士がお互いを知り合うことの手助けをしよう。そのための仕組みを作り発展させることで、「若者たちの心に火を点す」